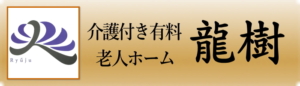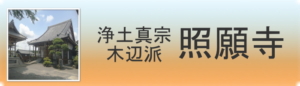保育方針
基本方針
・子どもの発達保障
子どもの特性に即し「発達の主人公」「生活の主人公」に育てる
・エンパワメントの実現
保護者が自己実現できる子育て支援を行う
地域に根ざす福祉施設としての役割を果たす
職員が良質の福祉サービスを提供する働きがいのある職場を構築する
・施設の経営の安定
必要な福祉サービスを提供する福祉施設として経営の安定を図る
支援目標
・じょうぶな身体(健康)
・たしかな考え(理性・認識)
・ゆたかな心(感性・情緒)
・よき仲間(協調性・社会性)
子どものためになる支援(最善の利益) –保育目標を実現する保育の構造-
1.基本的生活
「自分の生活は、自分で作る」という目標を掲げ、子どもの心と身体の成長、
発達に即した「身辺自立」と「生活文化(生活スキルやマナー)」を育みます。
2.あそび活動
子どもの発達を主導するもっとも大切な活動。
心身の発達に即した遊びの「楽しさ」や「創造性」、「社会性」を育みます。
3.自治活動
庭掃除や拭き掃除、話し合いを行うことで「生活文化」を育みます。
動物の世話や栽培を通して、「生活技術や助け合い」を体験的に学んでいきます。
4.学習活動
学校から出される宿題を中心に、「自ら取り組める環境」を用意します。
必要に応じて小道具も使うことで、頭と身体の両方で効率よく学んでいきます。
(辞書やおはじきなどを使用し、知識や技術を体得します。)
本園保育の思想的根拠
◆「自然は子どもが大人になる前に子どもであることを望む。
もしこの順序を乱そうとすれば、味わいのない、
すぐに腐敗してしまう早熟な果実を生み出すばかりだ。」
‐ ジャン・ジャック・ルソー (1712~1778)
ルソーは、子どもの教育に対して、大人がアレコレと口を出す流れではなく、
子ども自身が自発的に行動し、大人はあくまでもそれを補助する存在であるべきという、
「消極的教育法」を自身の教育論の根源としていました。
◆「遊びやせんとや生まれけむ、戯れせんとや生まれけん。
遊ぶ子どもの声聞けば、わが身さえこそゆるがれるれ」
– 『梁塵秘抄』 (編.後白河法皇)
一心に遊ぶ子どもたちの声を聞くと、彼らの純真さ・無邪気さに引っ張られるように
自分たちの体と心が動かされ、子どもの純粋なエネルギーが大人たちにも影響を与える
ということから、子どもたちへの愛情と尊厳を再認識しようといった詩になっています。
◆「人生に必要な知恵は、すべて幼稚園の砂場で学んだ」
– ロバート・フルガム (1937~)
単純に砂場で遊ぶことで知恵を得るというわけではありません。
人は、充実した人生を送るために必要なことをすでに大体知っていることに
そのうち気付き、それは全部幼稚園で学んだことだったということに思い当たります。
大人になって心身共に健全な生活を送るために、幼児期に何を教え、
何を感じてもらうかをしっかり考えて育児に取り組む重要性を説いたものになっています。
◆「「知る」ことは「感じる」ことの半分も重要ではない。子どもたちがであう
事実のひとつひとつが、やがて知識や知恵を生みだす種子としたら、
さまざまな情緒や感受性は、この種子をはぐくむ肥沃な土壌です。
幼い子ども時代は、この土壌を耕すときです。」
– 『センス・オブ・ワンダー』 (著.レイチェル・カーソン)
教育と称して知識を詰め込んでいくのではなく、子どもたちが自然を通して何かに出会い、
その出会いに対して何かを強く感じるとき、その先に確固たる知識や知恵が生まれ、
後に生き生きとした精神力へとつながっていきます。
大人になるにつれ、はじめて出会うもの・経験するものが減っていき、驚きや感動といった
感性を手放してしまうかもしれません。今一度、子どもの経験について考え、
一つ一つの出会いを大事にできるようにサポートしていこうといった詩になっています。
◆「自由感、精進感」
– 倉橋 惣三 (1882~1955)
何かに取り組むとき、あるところまで仕上げないと気が済まない欲求、
ただ取り組むだけではなくなるべく上手にしたいという衝動。
窮屈であるが、自ら求めるところがあるそれを「生活の自由感」に対して、
「生活の精進感」と倉橋は名付けました。
この精進感を、義務や我慢で縛り付けるのではなく、子どもが持つ自然な欲求として
満たしていけるように大人が見守っていくことを説いたものになっています。